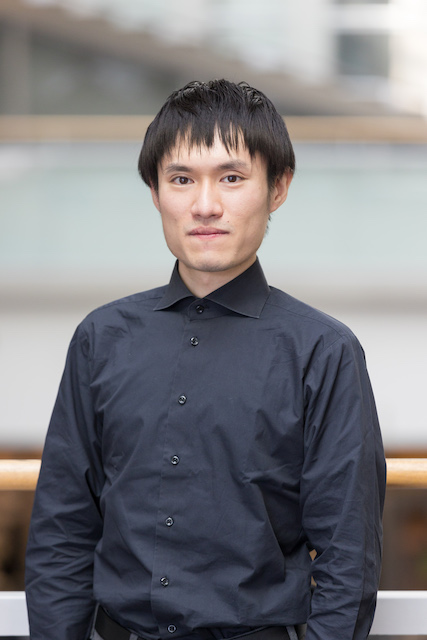JOURNAL
ハルサイジャーナル
東京・春・音楽祭2021
リッカルド・ムーティ「イタリア・オペラ・アカデミー in 東京」vol.2 《マクベス》
開催レポート Part 4
巨匠リッカルド・ムーティによる「イタリア・オペラ・アカデミー」。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、1年延期を経て開催となった第二回目のアカデミーでは、ヴェルディの《マクベス》を題材に約2週間に亘りムーティによる熱き指導が繰り広げられました。初日の《マクベス》作品解説から、本年に限りインターネットで無料公開されたアカデミー講義、そして集大成の《マクベス》公演まで。音楽ライターの宮本明氏にレポートしていただきます。
Part 4は4名の指揮受講生をご紹介します。
文・宮本 明(音楽ライター)
今回の「イタリア・オペラ・アカデミー in 東京」の指揮受講生は次の4人だった。
・チヤ・アモス Chiya AMOS(シンガポール)1990年生まれ
・ヨハネス・ルーナー Johannes LÖHNER(ドイツ/アメリカ)1990年生まれ
・高橋達馬 Tatsuma TAKAHASHI(日本)1989年生まれ
・湯川紘惠 Hiroe YUKAWA(日本)1993年生まれ
※ 画像をクリックすると、拡大表示します。
photos : ©増田雄介
アモスとルーナーは2019年のアカデミー vol.1《リゴレット》からの連続受講。日本勢は、マスタークラス初日午前中に行なわれたオーディションに合格しての新規受講だが(ぎりぎり直前にオーディションがあるのは前回と同様)、昨夏ラヴェンナの本家「イタリア・オペラ・アカデミー」でも第1次選考を通過していた二人。コロナ禍で第2次選考以降の参加が叶わなかったが、今回、現地からの推薦もあって参加し、見事チャンスをものにした。
活動歴を見ると、4人の中で最もキャリアがあるのはアモス。ロシアを拠点として、2017年にウラジカフカに開場したマリインスキー劇場の北オセチア・アラニヤ支部の指揮者に就任、今シーズンからはサンクトペテルブルクのユース・オーケストラ、キーテジ管弦楽団の首席指揮者も務めている。昨年はコロナ禍で演奏の機会を奪われ、シンガポールに戻ってフード・デリバリーのアルバイトで自転車を漕ぐ姿が海外のTVニュースで取り上げられて話題にもなった。そのことを本人に聞くと「生き残るためだから。若い指揮者は地に足をつけて生きなければならないんだ」と平然。たくましい。
ドイツ系アメリカ人のルーナーも、2018年からレーゲンスブルク室内管弦楽団の音楽監督を務める一方で、すでにヨーロッパの複数の名門オーケストラに招かれて頭角を現しつつある存在。「前回参加の時にはムーティに自分をアピールするところから始めなければならなかったけれど、今回はより自分らしく振る舞えたと思う」とルーナー。その〝彼らしさ〟ということなのかどうか、「(指揮者の)背後にいる歌手と、どのようにコミュニケーションを取るか」というムーティの問いに、お尻を振ってみせて、ムーティを苦笑させていた。陽気な人だ。
高橋達馬は東京芸術大学・大学院を経て、2016年からベルリンのハンス・アイスラー音楽大学で学び、現在もベルリン在住。同じベルリンを拠点とし、前回のアカデミー参加後にブザンソン国際指揮者コンクールで優勝を果たした沖澤のどかからも、「すごいから絶対に受けたほうがいい」と勧められていたのだそう。ヨーロッパの劇場で仕事を得ようと応募しても、30歳過ぎのアジア人にとっては、オーディションにこぎつけることさえ難しいそうで、このまま地味に埋もれていくのかと不安に駆られていた時期もあったそうだが、今回ムーティのレッスンに接して、地道に勉強してきたことも無駄ではなかった、少し自信を取り戻すことができたと手ごたえを語っていた。
最年少の湯川紘惠は昨年3月に東京芸大大学院を修了したばかり。前回の《リゴレット》を毎日最前列で聴講して、いつかは自分もレッスンを受けたいと思っていたという。若い指揮者がオペラを振る機会はなかなかない。オーケストラ伴奏で、プロの歌手を相手にオペラを指揮したのはこれが初めて。「赤ちゃんみたいな状態」だったというからなおさらなのだろう、アカデミーを通して確かな成長を自分でも感じることができたという。ここからがスタートと語っていたが、7月には英国ロイヤル・オペラ・ハウスのジェット・パーカー・ヤング・アーティスト・プログラムの短期マスタークラスにも参加するなど、着実に経験を積んでいる。
ムーティが彼らに指揮法やバトン・テクニックに関する指摘を与える場面はけっして多くないのだけれど、印象的だったアドヴァイスをいくつか拾ってみると─。
たとえば姿勢について。
「背中を伸ばして! もしワーグナーを6時間、そんなに前かがみで指揮していたら歩けなくなってしまいますよ!」
たしかに、ムーティの指揮する姿は美しい。もちろんつねに直立不動で振るわけではないけれども、立ち姿だけでも威厳を感じる。これについては、コンサートマスターを務めた長原幸太もこう語っていた。
「(指摘を受けた受講生が)だんだん姿勢が良くなりましたよね。やっぱりきれいに立ってくれると、こっちも美しい音を出そうと思うんです」
あるいは右手と左手の役割について。
「あなたはなぜいつも両腕で振るのですか? クセ? 私の先生は、両腕で振るな!と言うんです。なぜなら2本の腕が100パーセント同時に動くとは言えないから。ミトロプーロスは、右手はテンポ、左手は表現と言いました。もちろん、それをミックスすることはありますよ。でも、つねに両腕を使う必要はないと思います」
何度も繰り返したのが、休符を空振りするようにというアドヴァイスだった。
「(四分休符が3つあって、4拍目からオーケストラが出る小節で)休符を1、2、3と振ったほうがオーケストラが出やすいと思いませんか? 私はオールド・スクールの人間なので、現代的なスマートなやり方とは違うかもしれません。でもオールド・スクールはオーケストラを気持ちよくさせるんです。音がなくても、休符の雰囲気を確立してから始めなければ。怖れないで。モダン・スクールは洗練されていますね。でもリズムは失われがちです」
空振りをなるべく少なくして、上述の例なら、予備拍として「3」だけ、あるいは「3」のウラだけを示す〝スマート〟な指揮にアラートを鳴らす(てっきり、空振りしないほうが高度なやり方なのかとばかり思っていた)。もちろんケースバイケースで、見ているとムーティ自身も必ずしもそう振るわけではないのだけれど(目だけでも指揮できるとか、いろいろやって見せてくれた)、オーケストラがストレスなく、かつ安全に弾けるようにというのが基本なのは、とても納得。
他には、レチタティーヴォの部分の歌とオーケストラの合わせ方について指導する場面が目立った。歌手たちに自由に歌わせながら、どのようにオーケストラと合わせるか、どこから振り始めればいいか、歌手側の意識の持ち方など、問題となる箇所をひとつずつ、丁寧に説明し、自らやってみせる。歌手とオーケストラの呼吸や生理を合わせるような作業。1箇所ごとに異なる対処が要求されるから、経験が大きく物を言いそうで、受講生たちも簡単ではなさそうだった。
本稿執筆にあたり、ヨーロッパにいる高橋達馬と湯川紘惠にあらためて話を聞いた。
(高橋達馬の話)
「最初は言葉では表現できないような緊張をしました。でもマエストロはとても温かい人で、若い人を助けることを本当に使命と感じて背負っているのがわかります。一人一人のこと考えてくださって、あんな人はあまりいないのではないでしょうか。とにかくぶれない。それだけでも大変なエネルギーですよね。
スコアに忠実であることに厳しいのはもちろんですが、実際にはスコアに書いてないテンポの動かし方もしていて、それはたとえばイタリア語の歌詞がこうだからアッチェレランドなのだとか。あるいは細かい音符のちょっとしたニュアンスの出し方など、受け継いた伝統だけではなく、スコアを見て、深く考えてらっしゃるのがわかります。そういう細かいことは、なかなか教えてもらえることではないと思います。
オペラはずっと自分には無理だと思っていたのですが、2年前から歌手たちの伴奏をする仕事を始めて、関心を持つようになりました。いいタイミングでアカデミーに参加できて、運が向いてきたのかなと思っています。もっと早くやれればよかったのですけど、後悔しても仕方ない。今は可能な限りオペラの勉強に時間を使おうと思っています。若いうちに主要なレパートリーは勉強しておきたい。その勉強のプロセスの中で、ムーティ先生から学んだことが生きてくると思うんです。
僕の知る限り、指揮のマスタークラスは、普通はもっと受講生が多くて、実際に一人が指揮する時間は合計でせいぜい1時間程度です。このアカデミーはそれを4人だけで分け合って、しかもそこにずっとマエストロ・ムーティがいるのですから贅沢です。こんなにポジティブな経験はなかなかできません。受けられるのなら次回もまた自分が受けたいので、仲間には紹介しません(笑)」
(湯川紘惠の話)
「母が声楽を勉強していたので、生まれた時から歌は身近にありました。だからずっと歌が好きだったのですが、オーケストラと一緒にオペラを勉強するのは初めて。すごい経験をさせていただきました。本当に夢のような時間。無我夢中でした。
初日に真横に立って見た、ムーティ先生の溢れ出る圧倒的なオーラは忘れられません。若い音楽家を育てたい、音楽を伝えたいという、マグマのような情熱を感じました。
ムーティ先生が作品や作曲家への尊敬と愛、楽譜の奥に見てらっしゃる世界を表現するために、強弱やテンポ、求める音への妥協なさらない姿に感銘を受けましたし、それが真実なのですよね。特にピアニッシモの作り方は奇跡でした。楽譜を信じられないくらい真摯に読み取っていらっしゃるのだなと感じます。駆け出しの私のパレットにない色を、魔法のようにたくさん見せていただいたような気がしています。
そんな経験のおかげで、最近少し、自分の音がちゃんと聴けるようになったような気がしているんです。たとえば、スコアをピアノで弾いて勉強する時に、音楽の流れをイメージして作るようになったというか。以前はただ音を鳴らすだけで満足していたのが、自分を客観的に見て、考えてトライすることが増えたように思います。鮮やかなパレットを見せていただいて、つねにもっと可能性があるのだと考えるようになったのかもしれません。
最終日、感謝と感じたことをお手紙にしたためてお渡したところ力強くハグしてくださったのが、『頑張れよ!』と言っていただいているような気がして、大きな勇気をもらいました。音楽に対して、妥協せず、真摯に生きられたら。それを続けられるように心がけたいと思っています」
(つづく)