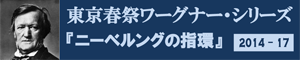JOURNAL
ハルサイジャーナル
連載 Wagneriana ワグネリアーナ
~ワーグナーにまつわるあれこれ 2
第2回 フランス文学界のワグネリアンたち
文・松本 學(音楽・バレエ・映画評論)
ワーグナーの周辺情報を紹介することで、この19世紀の大作曲家に興味を持っていただこうというのがこのコラム。前回は音楽が話題だったので、今回は文学界について触れてみたい。
ワーグナーに強く関心を持った作家といえば、たとえば『悲劇の誕生』を書いたフリードリヒ・ニーチェ(1844~1900/思想家や文献学者というべきだが、ここでは広い意味として作家とする)や、講演集『リヒャルト・ヴァーグナーの苦悩と偉大』のトーマス・マン(1875~1955)などがまずは想い出される。ドイツの作曲家なのだからドイツで名が知られるのは、まあ当然と言えば当然。巨人ワーグナーの名声は自国内で留まるはずもなく、さらにはお隣フランスでも相当に話題となり、注目されてゆく。
フランスでのワーグナー人気
大いなる野望に溢れていたワーグナーが、当時ヨーロッパの文化の中心であったパリでの成功も夢見ていたのは言うまでもない。彼が最初にパリの地を踏んだのは1839(~41)年。その後、1849年にはドレスデンの3月革命(5月蜂起)の失敗から逃げて、また翌1850年にはリストや最初の妻ミンナに勧められて渡仏している。ロンドンへの演奏旅行の際に立ち寄ってパリ万博を楽しんだのが1855年。1859~61年には長期滞在し、1867年には再び1週間ほどパリ万博観光と、数度にわたってこの街を訪れている。このうち、重要なのは最初の1839~41年と、《タンホイザー》上演を含む1859~61年の2度の逗留だ。
リガの楽長の座を失った直後だった前者では、最初期の歌劇《恋愛禁制》が、会場のルネサンス劇場の倒産で上演直前にお流れになってしまったこともあって、彼は経済的にきわめて困窮していた。そんなワーグナーを助けたのは、先にこの街に亡命していた詩人ハインリヒ・ハイネ(1797~1856)で、ワーグナーは彼に紹介された出版社で記事を書いて糊口を凌いだ。また、《タンホイザー》のアイディアを得たのも、ハイネからと言われている。
後者1859~61年の滞在以降では、いよいよフランス人作家たちの注目が顕著に現れる。特にこの時にシャルル・ボードレール(1821~67)に絶賛されたのは大きく、これによってステファヌ・マラルメ(1842~98)やマルセル・プルースト(1871~1922)、ポール・ヴァレリー(1871~1945)といった名だたる文人たちの評価が続いたと言っても過言ではないだろう。プルーストは『失われた時を求めて』にワーグナーの名前を何度も登場させているだけでなく、この小説自体が《パルジファル》の影響を指摘されているし、またヴァレリーはワーグナーの音楽をおおいに気に入って足繁くコンサートに通っていたようだ。
ボードレールとマラルメのリアクションはより明確で、ボードレールは1860年のコンサートや1861年3月にオペラ座で上演された《タンホイザー》(ジョッキー・クラブの妨害により3回で中止)を観て以降、「我が音楽」と呼んで、ワーグナーを讃える有名な記事『リヒャルト・ワーグナーと《タンホイザー》のパリ公演』を書いた。
マラルメはエドゥアール・デュジャルダン(1861-1949)の創刊した雑誌『ワーグナー評論』のために85年に論文を、翌86年にもソネ『礼讃(Hommage)』を書いている。ただし彼の場合、この論文を書く前にどの程度ワーグナー音楽の実演に触れていたかは怪しい。というのは、84年にデュジャルダンに連れられてラムルー管弦楽団で聴いてはいるようなのだが、先の論文発表直前に「私は1度も観たことがない」と書き記しているからだ。84年にラムルーは《トリスタン》を上演しているが、彼が聴いたのはそれとは別の、抜粋によるオーケストラ・コンサートだったのではないだろうか。
ちなみに記録としてわかっているマラルメのワーグナー体験は、91、93年の頃に行われたラムルー管による楽劇の抜粋公演だったようで、オペラ座で《ヴァルキューレ》を"観た"のは93年5月とある。それ以前、87年にも《ローエングリン》を観にエデン座に行くはずだったが、こちらは延期騒動の末に機会を逸してしまった。実際に観ていない相手に原稿を依頼するだろうか?とも思うが、マラルメほどのビッグネームだとあり得るような気もしないではない......。
ラムルーがコンサートで抜粋を採り上げていたことは、ジョリス=カルル・ユイスマンス(1848~1907)の小説『さかしま』からもわかる。ここでは、指揮者ラムルーのことを表すのに、「空中でソースを掻き混ぜるような恰好でタクトを振り、[中略]ワーグナーの楽曲から引きちぎられた楽章を、下手くそな演奏で滅茶苦茶にしている」とある。なんとも辛辣な言い回しだ。
作家リラダンのワーグナー熱
《タンホイザー》や《トリスタン》を観たピエール・ルイス(1870~1925)は、バイロイト詣でで感激した《パルジファル》と自らが同化しようと修道院に籠ったそうだ。酒やタバコ、幻想と瞑想を手段にチャレンジしたものの、結果は6日で6キロ痩せただけで、あえなく追い出されて終了。ちなみに彼の小説『女と人形』をもととするルイス・ブニュエルの遺作映画『欲望のあいまいな対象』(77)では、最後にちらりとワーグナー(《ヴァルキューレ》第1幕 第3場)が流れる。まあ偶然だろうが。
その他、ジェラール・ド・ネルヴァル(1808~55)は1850年8月20日、ヴァイマールで《ローエングリン》を観て、そのリポートを書いているし、エミール・ブールジュ(1852~1952)は『神々の黄昏』という小説を書き、その中にヴァルキューレも織り込んだ。テオフィル・ゴーチエの娘ジュディット・ゴーチエ(1850~1917)とは恋仲まで囁かれている(プラトニックだったとも言われるが)。
そのジュディットが、スイスのルツェルン郊外トリープシェンのワーグナー邸(現在のワーグナー博物館)を訪れた際の記録が『ワーグナー訪問記』。そして、この時に同行していたのが、当時の夫で、『童貞王』というルートヴィヒ2世とワーグナーに関する著作を遺したカチュール・マンデス(1841~1909)と、オーギュスト・ド・ヴィリエ・ド・リラダン(1838~89)である。
最後にこのリラダンという作家を簡単にご紹介しておこう。ブルターニュの名門貴族の出の彼は、23歳だった1861年に《タンホイザー》を観劇し、すっかりハマってしまう。その後、ボードレールにワーグナー本人を紹介され、ワグネリアンとして決定付けられた。1869年には、上述のようにトリープシェンを訪ね、自作の戯曲『反抗』を朗読し、ワーグナーに「本物の詩人だ」と絶賛される(さぞかし舞い上がったことでしょう)。またワーグナーが《ヴァルキューレ》をピアノで弾いてくれたのに感激し、記事を遺している。さらに翌年も訪問。この時はサン=サーンスの伴奏でワーグナーが《神々の黄昏》を歌ったそうだ(ワーグナーはジュディットが大のお気に入りで、彼自身もリラダンたちはともかく、彼女の訪問が嬉しくてしかたがなかったらしい。勢い余って木に登ったりもしたようだ。ヤレヤレ)。
さて、リラダンの小説にも、ワーグナーの影が垣間みられる。たとえば、"アンドロイド(人造人間)"という言葉を初めて用いたとされる『未来のイヴ』(押井守の『イノセンス』は、この小説の引用で始まる)。ここではエワルド卿いわく、きわめて美しいが「つける薬のない(=知性のかけらもない)女」アリシヤ・クラリーが登場するが、彼女に幻滅する理由のひとつとしてワーグナー音楽への無理解が語られる。そして、「雄渾な作曲家ワーグナーのヴィーナスのあらゆる燃えるような魅惑の力を授け」て彼女を複製しようとするのである(第4章「奇蹟の前提」)。また、《指環》の影響が指摘される劇詩『アクセル』では、主人公アクセル伯自体がワーグナー的とも言われるし、廃れてしまった楽器シャポー・シノワ※のかつての名手を主人公とする『昔の音楽の秘密』は、ワーグナーに捧げられた短編だ(ちなみに『トリスタン博士の治療』という短編もあるが、これは無関係)。さらに、彼はピアノが弾けたので、ボードレールやマラルメのためにワーグナーの音楽を弾き聴かせたりもしていたという(自ら作曲もした)。
このように文学者たちをも虜にしたフランスのワーグナー熱は、すぐさま音楽家たちにも拡散していった。次回はその中から、ドビュッシーを採り上げる予定。
【参考文献】
リラダン
『未来のイヴ』(創元ライブラリおよび『リラダン全集2』東京創元社)
『昔の音楽の秘密』(『リラダン全集1』「残酷物語」所収、東京創元社)
『アクセル』(『リラダン全集3』東京創元社)
※シャポー・シノワ(Chapeau Chinois)は次のCDで聴くことができる。
『Die Volksmusikinstrumente der Schweiz』(Claves: 509621)