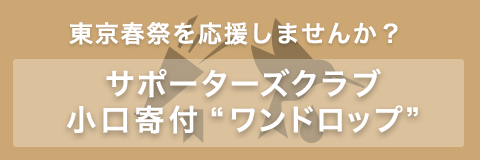JOURNAL
春祭ジャーナル
ふじみダイアリー 今日のハルサイ事務局
巨匠ムーティが次世代に伝えるヴェルディの魂! アカデミーが始まりました
桜の季節があっという間に駆け抜けていった上野公園。今は鮮やかな新緑に包まれて初夏のような清々しさです。中盤戦の東京・春・音楽祭。のこり期間の公演を充実した内容でお贈りできるよう、今できることに全力で取り組んでまいります。どうかご声援ください! 「ふじみダイアリー」では、ハルサイにまつわるさまざまな話題をピックアップしてお伝えしています。
4月9日(金)のリッカルド・ムーティによる《マクベス》作品解説で幕を開けた「イタリア・オペラ・アカデミー in 東京」。ユーモアを交えたサービス精神たっぷりのレクチャーに、熱心なお客さまが集まった東京文化会館大ホールの客席が沸きました。
この日の作品解説は、アカデミーのエッセンスを伝える、いわばムーティの所信表明演説です。現代において、ヴェルディがいかに誤って解釈され、聴衆もそれを歓迎してしまっているか。象徴的な例として挙げられたのは、歌手たちがこれみよがしに、ときにはヴェルディの書いた音を変えてまで高音をのばす習慣です。
「まるでショーの要素のひとつになってしまった。『ゴーーール!』と、サッカーにたとえているテノールまでいる。あるいは背中の曲がったリゴレットが、高音をのばすために、そこだけ背中をピンとして歌ったり」
と嘆きます。一流の演劇人でもあるヴェルディがそんなグロテスクな行為を許すはずがなく、それを聴衆がもてはやすのは、それが誤った「イタリア」を思い起こさせるからなのだと皮肉っぽいユーモアを交えて。
「太陽! 海! モッツァレッラ! トマト!…。それが多くの皆さんの考えるイタリア。でもイタリアにはダンテもラファエロもミケランジェロもいる。それが本当のイタリアなのです」
そうした間違ったイタリア・オペラの伝統を忘れて、今こそヴェルディを本当に理解するときなのだと、熱を込めて語ってくれました。
作品解説後半は歌手たちが加わっての公開レッスンです。参加したのは、アカデミー受講生の若い指揮者たちが指揮する「リッカルド・ムーティ introduces 若い音楽家による《マクベス》」(4月20日)に出演する日本人歌手の皆さん。マクベス夫人役の谷原めぐみさん(ソプラノ)、マクベス役の青山貴さん(バリトン)、マクダフ役の芹澤佳通さん(テノール)、バンコ役の加藤宏隆さん(バス・バリトン)、マルコム役の城宏憲さん(テノール)、侍女役の北原瑠美さん(ソプラノ)。
じつは皆さんの参加は、前日に突然言い渡されたのだそうです。ムーティに直接会ったのはこの日が初めて。それでいきなりのステージ。しかも舞台に出てみたらマエストロが自らピアノを弾くというので、さぞ驚かれたと思います。誰がどこを歌うのかもいっさい知らされていなかったそうで、それで堂々と歌ってみせるのは、皆さんさすがです。
ムーティは、《マクベス》ではとくに声の使い方が大事だと説きます。音楽的にではなく演劇的に、俳優のように、と。その最たる例はマクベス夫人の登場のアリアの前にある、手紙を読むシーンでしょう。音符のない、台詞だけの表現が難しい箇所です。
「けっして大声で読んではいけません」
オーケストラが繊細なピアニシモで弾いているのに、突然朗々と響き渡る声でやって台無しにする歌手がいるのだそう(ムーティは、名盤として知られるフィオレンツァ・コッソットとの録音のとき、ここを彼女と念入りに練習したエピソードを話してくれました)。
谷原さんのマクベス夫人。
「それだとちょっと甘すぎるかな」
など、ニュアンスを細かく指摘するムーティのアドヴァイスで、繰り返すたびに、表現が見事に変化していきました。
約2週間のアカデミーで、歌手の皆さんもムーティからヴェルディの魂を受け取っていきます。レッスンの模様は連日無料配信でご覧いただけますので、ぜひご注目ください。
関連ニュース
【4/10〜4/16無料配信】リッカルド・ムーティ イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.2《マクベス》アカデミー聴講プログラム/リハーサル関連公演
東京・春・音楽祭を応援しませんか