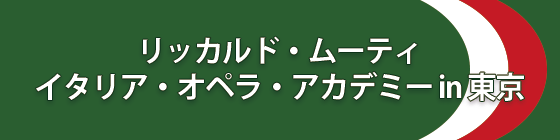JOURNAL
ハルサイジャーナル
リッカルド・ムーティ イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 vol.2《マクベス》
アーティスト・インタビュー ~青山 貴(バリトン)&谷原めぐみ(ソプラノ)
「目の前にマエストロがいて、そこで自分が歌っている。僕はいったいどこにいるんだろうと、不思議な感覚です」(青山 貴)
「本当! 夢の中にいるみたいです」(谷原めぐみ)バリトン青山 貴とソプラノ谷原めぐみ。巨匠リッカルド・ムーティが指導するイタリア・オペラ・アカデミー in 東京の、「若い音楽家による《マクベス》」(4月20日・ミューザ川崎シンフォニーホール)に題名役とマクベス夫人役で出演する主役二人に、ムーティのレッスンの様子など、このプロジェクトでの体験を聞いた。
文・宮本 明(音楽ライター)

青山 貴(バリトン)
青山「マエストロは何度も繰り返し『テアトラーレ(演劇的に)!』とおっしゃって、より劇的な表現を求めています。いつもだと、それがときには喉の負担になったりするのですけど、マエストロと一緒に歌っていると、いつの間にかできている自分に気がつくんです」
谷原「マエストロが立っていてくれているだけで、たとえ背中を見ているだけでも、なにかを引き出してくれます。
じつはマクベス夫人は自分のレパートリーではなかったし、オファーをいただいたときは、彼女の性格が私の声に合わないんじゃないかと思ったんです。だから自分がどう変わるんだろうとどきどきしながら準備してきました。ヴェルディの伝統をマエストロから直に受け取っているのは、なんと大きいことか。でもまだまだ。もっと何かを身につけたいと、もがいているところです」
ムーティは、「ヴェルディがこの2つの役に求めているのは美しい声ではない」と繰り返し説いている。必要なのはもっと言葉に合った声、引きずるような表現。それだけに俳優のような演劇性を求める。マクベス夫人の登場のシーン、歌の前にまず、音符のない手紙を読む台詞で始まるのは象徴的だ。
谷原「最初に言われたのが、目のことでした。『君の目! それじゃないよ』。声で演じることも必要ですが、表情、顔つき、すべて役になりきらないと。もちろんオペラ歌手は歌い手であると同時に役者でもあるのは当たり前で、いろんなものを持っていないとダメなのですけど、今回はそれをより深く感じています」

谷原めぐみ(ソプラノ)
と謙虚に受け止めるが、彼女の奥行きの深い声自体が、その演劇的な表現にじつにふさわしい。マクベス夫人のパートは、音域が、とくにソプラノにとっては下に広い難役だと思う(実際、ムーティは録音[1976年]ではメゾ・ソプラノのフィオレンツァ・コッソットを起用している)。高いシ♭から低いシ♭まで、2オクターヴ(!)を音階で一気に駆け下りる離れ業があったり、こと切れる直前には高いレが最弱声で要求されている。
無料配信されているアカデミーのレッスンの様子を熟視したが、谷原はそんな難所も、(しかも歌手にとってはコンディションの調整が難しい午前中の稽古でも)なんの不安も感じさせずに歌いきって、声楽的な基盤の確かさを感じさせた。
一方のマクベス役も、やはり声楽と表現の両立が難しいという。犯した罪への悔悟と不安、恐怖に苛まれて正気を失っていく心理を、バリトンの高域の弱声で表現しなければならない。
青山「マクベス役に気持ちよく声を出せる箇所はひとつもないと書いてある解説を読みました。まさにそんな感じで、朗々と歌えるのは第一声ぐらいじゃないでしょうか。つねに悩んで苦しんで。それをどうやって表現したらいいのか。マエストロがよく『cupo(暗く)!』っておっしゃるんですけど、それができたときは、物語の意味がつながっていくような気がします」
たしかに、配信を聴講していても、この「つながり」という視点は、ムーティが伝えたい、重要なキーワードのように感じた。
青山「とにかく音楽を止めないこと。ときどき僕が勝手にテンポを緩めて歌って間延びさせてしまって叱られてます(笑)。オーケストラも同じなのですが、緩めずに演奏するのを聴いていると、なるほどその通りだなあとわかるんです。演劇的につながっていくためには、テンポが前に進んでいかなければならない。もちろん緩めるところは緩める。言葉に即して、なのでしょうね。だからオーケストラも含めて、言葉を理解しなければならないのだと思います」
とはいえ、逆にいえば青山の場合、ムーティがたびたび止めて注意を与えるのは、ほぼそのイタリア語のことだけだったともいえる。青山の、(とくに弱声の)類まれな美しい声には巨匠も一目置いたようで、彼に話しかけるときは終始柔和だったし、「あなた、きれいな声ですね」とストレートな賛辞も贈っていた。もっとも、ことマクベスに関してはムーティが美しい声を求めていないというのは上述のとおりだから、簡単ではない。
青山「声の使い方ですよね。『その声がお前を殺す』とも言われました(笑)」
「若い音楽家による~」は、アカデミー受講生の指揮者たちが、《マクベス》抜粋を交代で振り分ける演奏会形式の公演。
青山「演奏会形式は、もちろん歌だけで勝負させていただくというプレッシャーもありますが、それだけに、ストーリや登場人物の気持ちを音楽でわかっていただけたときの充実感は大きいです。だから、音楽をもっと深めて行かないと。それがまさに今、マエストロとやっていることです」
谷原「マエストロが、オーケストラは伴奏じゃなくて、合唱、ソリスト、オーケストラが相互に作用しながら共同で作っていくものであると言った途端に、オーケストラが変わったような気がしたんです。とくにオーケストラとソリスト、合唱が同じ舞台の上で演奏する演奏会形式だと、その相互作用も一目でわかると思いますので、ぜひ注目してほしいです」
最後に、それぞれの役で一番好きな場面歌いどころ、聴きどころを教えてもらった。
谷原「言っちゃっていいですか?(笑)やっぱり第4幕の夢遊の場です。あんなに強かったレディが精神に異常をきたして死んでしまう。それを音楽の中で表現するのは気持ちがいいです!」
青山「僕は、第3幕の、次々に出てくる王たちの幻影に会う場面。劇的で大好きです。あ、でも今回のミューザ川崎は抜粋上演なので、この場面は歌わないのですけど……(笑)。そうだ! 結局そういう、本番で歌わないところも全部レッスンしてくださったんですよ。本当にうれしいことです」
持ち前のポテンシャルの土台の上に、アカデミー期間を通してムーティの薫陶を受けた二人の《マクベス》に、大いに期待している。いまこの瞬間、世界中のオペラ歌手のなかで、ムーティのイメージするマクベスとマクベス夫人を直接、誰よりも濃厚に受け止めているのがこの二人なのだから。
photos : ©飯田耕治