春祭ジャーナル 2012/01/30
ようこそハルサイ〜クラシック音楽入門~
いにしえの声と静寂に、J.S.バッハが出会うとき~[東博でバッハ]

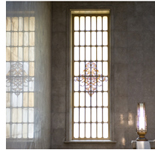

東京国立博物館 ©青柳 聡
ときどき思い出したように『午前3時のスクリャービン』というコンサートができないものかと考えている。ピアノがそっと和音を鳴らすと淡い音の香りがたちこめ、小さな空間を満たしていくようなスクリャービンの音楽を、ひっそりと静まりかえった午前3時に味わう。それは「音楽を聴く」という鑑賞行為ではなく、「響きを感じる」という音と聴き手のセンシティヴなコミュニケーションだ。
夜中にひとり、自分の部屋でそっと(ごく小さな音で)J.S.バッハの《フーガの技法》を聴くというような行為も、おそらくそれに近いだろう。音楽そのものに集中するだけではなく、自らの感性を研ぎ澄ませてその場の空気感を味わうことができるのなら、音楽は別の顔を見せてくれるはずだ。理想的とされる残響が用意された音楽ホールだけが、いい音楽を味わう条件を備えているわけではない。
東京・春・音楽祭では毎年、美術館や博物館でのコンサートがたくさん開催される。中でも『東博でバッハ』と題されたミュージアム・コンサートは、個人的にとても気になるシリーズだ。「和」というキーワードのもとに集まる多くの展示品や所蔵物、時間を超越して現代に伝えられた古代文化の粋などが息づく東京国立博物館には、建物の中に独特の時間が流れているような気さえする。私たちはその時間に足を踏み入れるのだが(と書くと、なんだか『トワイライト・ゾーン』のようでもあるけれど)、そこで生まれるJ.S.バッハの響きと音のたたずまいは、言うまでもなくその場そのとき限りの存在。作曲家の魂が降りてきて、館内の美術品や仏像などと、私たちには聞こえない会話をしているような妄想を抱いてしまう。
そうした空間で、卓越した音楽家たちによるJ.S.バッハを聴く。それはきっとコンサート・ホールでは味わえない体験であり、J.S.バッハの音楽が静謐な「和」の精神に溶けこむ様子を目撃する時間なのだ。
~関連公演~
「東博でバッハ」
【2014】
vol.17 福田進一(ギター)
vol.18 三浦文彰(ヴァイオリン)
vol.19 山崎伸子(チェロ)& 小林道夫(チェンバロ)
vol.20 川崎洋介(ヴァイオリン) vol.21 ウェン=シン・ヤン(チェロ)
【2013】vol.19 山崎伸子(チェロ)& 小林道夫(チェンバロ)
vol.20 川崎洋介(ヴァイオリン) vol.21 ウェン=シン・ヤン(チェロ)
vol.12 郷古 廉(ヴァイオリン)
vol.13 福田進一(ギター)
vol.14 川本嘉子(ヴィオラ)
vol.15 寺神戸 亮(ヴァイオリン) vol.16池上英樹(マリンバ)
【2012】
vol.7 田崎悦子(ピアノ) vol.8 ゴルトベルク変奏曲(弦楽五重奏) vol.9 高木和弘(ヴァイオリン)
vol.10 中野振一郎(チェンバロ) vol.11 福田進一(ギター)
vol.15 寺神戸 亮(ヴァイオリン) vol.16池上英樹(マリンバ)
【2012】
vol.7 田崎悦子(ピアノ) vol.8 ゴルトベルク変奏曲(弦楽五重奏) vol.9 高木和弘(ヴァイオリン)
vol.10 中野振一郎(チェンバロ) vol.11 福田進一(ギター)