JOURNAL
春祭ジャーナル
2014 / 15シーズンのマレク・ヤノフスキ
今春『ニーベルングの指環』の第二弾として《ワルキューレ》が上演される。指揮を担当するは、昨年に引き続き、ベルリン放送交響楽団の芸術監督を務めるマレク・ヤノフスキ。本稿では、ベルリン在住のジャーナリスト中村真人氏にヤノフスキの最新情報をレポートしていただいた。
取材・文:中村真人(ジャーナリスト/在ベルリン)
バイロイト・デビューが決まったヤノフスキ
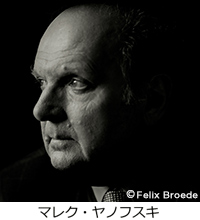
2014年11月12日、「指揮者マレク・ヤノフスキが2016年から2年間、バイロイト音楽祭で《ニーベルングの指環》を指揮!」というニュースがドイツの音楽界を駆け巡った。2013年に新演出上演されたフランク・カストルフ演出の《指環》を指揮したのは、もともとバイエルン国立歌劇場の音楽監督を務めるキリル・ペトレンコだった。この舞台の最後の2シーズンを、ヤノフスキが代わって指揮することになったというのである。
このニュースを、驚きをもって受け止めた音楽ファンは多かったのではないだろうか。なにしろ、ヤノフスキは1990年代以降、歌劇場でオペラをまったく指揮していないからだ。
ここでオペラ指揮者としてのヤノフスキの歩みをざっと振り返ってみたい。1939年ワルシャワで生まれたヤノフスキは、青年期までドイツのヴッパータールで過ごし、ケルンの音楽大学でヴァイオリン、ピアノ、及び指揮を学んだ。後に、アーヘン、ケルン、デュッセルドルフ、ハンブルクの歌劇場でコレペティトゥアやカペルマイスターを務めるなど、彼のキャリアは歌劇場から始まったのである。
1969年にハンブルク国立歌劇場のカペルマイスターになったヤノフスキは、最初の頃は1ヵ月の間に6つから7つのオペラをリハーサルなしで振ったという。『ベルリーナー・モルゲンポスト』紙のインタビュー(2013年12月)に、彼はこう答えている。「このとき私が味わったプレッシャーが、今日のオペラハウスでは過去のものになりました。それはいいことですが、反面、当時の若い指揮者はこの古いシステムの中で歌手に対していかに反応するかということを鍛えられたのです。私は多くのオペラを指揮することで、人間の声について多くを学びました」。
ニューヨーク・メトロポリタン歌劇場やウィーン国立歌劇場でも指揮したヤノフスキだったが、1970年代後半から台頭するレジーテアター(演出家主導の舞台劇)に嫌悪感を抱くようになったようで、ミュンヘン国立歌劇場での「特に風変わりな演出の経験」の後、歌劇場での仕事から去る決意をする。
「私は今でも時々、ワーグナーの《トリスタンとイゾルデ》、R.シュトラウスの《ダフネ》、モーツァルトの《コジ・ファン・トゥッテ》といった作品、あるいはプッチーニのオペラを振る機会がないのを寂しく思いますが、オペラハウスでの日常的な雑務については全く(寂しいと)感じません」と語るヤノフスキが、バイロイトの舞台に、しかも賛否両論が渦巻いたカストルフ演出の《指環》を指揮する日が来るとは感慨深いものがある。ペトレンコの降板は、音楽監督を務めるバイエルン国立歌劇場の夏のオペラ音楽祭と時期が重なることによる実際的な要因が大きかったようだが、それでもこの交代劇は近年のヤノフスキの円熟した仕事ぶりへの評価、中でも2010年から13年にかけて行われたベルリン放送交響楽団とのワーグナー・ツィクルスの成功なしには考えられなかったと言えるだろう。2016年夏には77歳を迎えているとはいえ、深くもぐり込んだバイロイト祝祭劇場のオーケストラピットからヤノフスキがどのような響きを引き出すか、期待は高まる。
11月の定期演奏会から 〜ハルトマンとベートーヴェン
さて、バイロイトのニュースの翌日、筆者はフィルハーモニーで行われたベルリン放送交響楽団の定期演奏会を聴いた。曲目はベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番(ピアノはポール・ルイス)とレオノーレ序曲第3番、そしてカール・アマデウス・ハルトマンの交響曲第6番。序曲、協奏曲、交響曲というシンフォニーコンサートの定番の組み合わせを、ヤノフスキは敢えて、協奏曲、交響曲、序曲という順番で並べた。
中でも興味深い体験だったのは、プログラムの中ほどに置かれたハルトマンの交響曲だった。現代作品はあまり積極的には取り上げないヤノフスキだが、ハルトマンの作品に対する評価は高く、2005 / 06シーズンでは同じ「アマデウス」のモーツァルトを組み合わせたツィクルスをベルリン放送響と披露している。
1953年に完成した交響曲第6番は、2つの楽章からなる。11月の公演では、陰鬱と悲痛さが支配するアダージョに続く第2楽章が圧巻だった。弦楽器の細かいリズミカルな動きがフーガに発展し、それがいったん収まって、今度はファゴットのメロディから他の木管楽器にテーマが受け継がれてゆく。やがて、ヴィオラから最後のフーガ的発展が始まると、ヤノフスキの巧みなリズム感のもと、ピアノ、6人の打楽器、2台のティンパニまで加わって圧巻の効果が生まれた。幾重も波のある複雑な構成の本作を、きっちりとクライマックスに向けて設計するヤノフスキの長所が発揮された。
最後はベートーヴェンのレオノーレ序曲第3番。通常は重々しく奏でる傾向にある導入部を、ヤノフスキは透明な響きでむしろ軽やかに進める。主部に入ると、キビキビとしたリズムから躍動的な音楽が立ち上がってくる。ハ長調の第一主題が高みに達する度に聴き手の気分は高揚し、コーダでは強烈な一撃と相まって凄まじい迫力が生まれた。最後の一音が鳴り止んだ瞬間、興奮した客席から叫び声が飛び交った。確実に音を積み上げていくことで「熱狂」を生み出せる指揮者。ベートーヴェンでこういう音楽を作り出せる人は意外と数少ないのである。
ハルトマンとベートーヴェンを並べて聴くことで、ナチス時代不遇の身にありながら自らの意志を貫いたハルトマンと、ベートーヴェン、そして《フィデリオ》のフロレスタンが重なり合うのを感じた。ヤノフスキならではのプログラム構成である。それはまた彼自身が2人の作曲家に共通する強靭な資質を持っているからでもあろう。
ヤノフスキはこの月、メンデルスゾーンのオラトリオ《エリア》、さらにオール・ラヴェルという対照的なプログラムを振って、それぞれ充実した成果を披露した。2015年春はベルリン放送響と来日公演を行い、その後、東京・春・音楽祭で《ワルキューレ》を指揮する。5月にはベルリンでR.シュトラウスの《ダフネ》と《エレクトラ》を豪華歌手陣のもと演奏会形式で上演する予定だ。この日の躍動感にあふれた指揮ぶりを間近で観て、ヤノフスキは今まさに心身ともに充実した音楽家人生を歩んでいると感じた。
