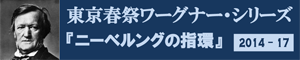春祭ジャーナル 2012/12/19
ワーグナー vs ヴェルディ 第1回「オペラの死に様」
 文・飯尾洋一(音楽ジャーナリスト)
文・飯尾洋一(音楽ジャーナリスト)
命を大切にしましょう。
思わずそうつぶやきたくなるくらい、よく人が死ぬ。
2013年にともに生誕200周年を迎える二大オペラ作曲家ワーグナーとヴェルディの作品の話である。記念の年に彼らの生を祝うよりも、むしろ彼らの登場人物の成仏を祈りたい。そう思うほど、二人のオペラでは命が粗末にされる。
ワーグナー作品には不審死が多い。「タンホイザー」のヒロイン、エリーザベトが物語の進行の裏側でいつの間にか死んでいるのも納得がいかないが、最後にタンホイザーが魂の救済と引き換えに(?)息絶えるのは、医学的にはどのような所見に相当するのだろうか。
「ローエングリン」の最後の場面も謎である。小舟に乗って去るローエングリンを見送ったエルザは、なぜ絶命するのか。悲嘆に暮れたからといって、そう易々と旅立たれても。
「さまよえるオランダ人」のヒロイン、ゼンタはオランダ人への愛と誠を誓い海に投身する。精神世界から見れば、二人は結ばれて昇天したことになるのだろうが、物理世界から見ればひどく苦しみそうな死に方である。オランダ人に至っては、最初から死んでいる。
ヴェルディ作品で怖いのは感情の暴発である。ハンカチひとつで早とちりをして妻を絞殺し、続いて自刃するオテロ。ラダメスの生き埋めの刑を予測して、先回りして地下牢に入って心中をスタンバイしているアイーダ。赤ん坊をわが子か敵の子かよく確認もせずに火に投げ入れる「トロヴァトーレ」のアズチェーナ。みな、もう少し落ち着いて物事に当たってはどうか。
ワーグナー作品では観念的な死の場面が多く、ヴェルディ作品では愛憎劇の果てに死が待ち構える。舞台作品において、最大のハイライトは愛、そして死。頻発する登場人物の死は、観客にカタルシスを約束する。
もし自分がワーグナーかヴェルディのオペラの登場人物としてこの世に生を受けることになったら、その作品世界が「ニュルンベルクのマイスタージンガー」であるか「ファルスタッフ」であることを祈るほかない。この例外的に喜劇的な両作品以外では、一瞬の油断も許されないのだ。
第1回「オペラの死に様」 | 第2回「ベストカップルはだれだ?」 |
第3回「親の顔が見たい」 |
第4回「おまえはもう死んでいる」 | 第5回「長いものには巻かれたい」
~関連公演~