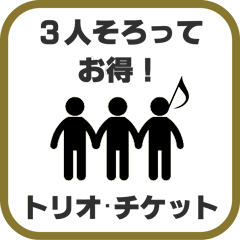東京・春・音楽祭-東京のオペラの森2018-
ミュージアム・コンサート東博でバッハ vol.40 島田真千子(ヴァイオリン) & 北谷直樹(チェンバロ)
オーケストラや室内楽、ソロと多方面で活躍するヴァイオリニスト島田真千子。バッハへの深い理解に定評のある彼女が共演を熱望したチェンバリスト、欧州で活躍する北谷直樹を迎えて挑む「ヴァイオリンとチェンバロオブリガートの為のソナタ」全6曲演奏会。
プログラム詳細
2018:04:04:19:00:00
2018.4.4 [水]19:00開演(18:30開場)
東京国立博物館 平成館ラウンジ
■出演
ヴァイオリン:島田真千子
チェンバロ:北谷直樹
■曲目
J.S.バッハ:ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ
第4番 ハ短調 BWV1017
I. Largo
II. Allegro
III. Adagio
IV. Allegro
第5番 ヘ短調 BWV1018
I. [No tempo marking]
II. Allegro assai
III. Adagio
IV. Vivace
第6番 ト長調 BWV1019
I. Allegro
II. Largo
III. Allegro
IV. Adagio
V. Allegro
第1番 ロ短調 BWV1014
I. Adagio
II. Allegro
III. Andante
IV. Allegro
第2番 イ長調 BWV1015
I. [No tempo marking]
II. Allegro
III. Andante un poco
IV. Presto
第3番 ホ長調 BWV1016
I. Adagio
II. Allegro
III. Adagio ma non tanto
IV. Allegro
【試聴について】
~春祭ジャーナル~
J.S.バッハの「ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ」(全6曲)は、1717年から23年にかけてのいわゆる「ケーテン時代」に作曲されたと推定される。バロック時代の「トリオ・ソナタ」の様式であるヴァイオリンが1声、チェンバロの右手が1声、そして左手で即興的に通奏低音を受け持つというスタイルを排して、チェンバロ・パートが右手・左手とも緻密に書き込まれている。また、時には重音を用いた和音で伴奏を付けるなど、バロック以降のスタイルを予感させる書法も目立つ。チェンバロに重要な役割を与えたことに関しては、同時期に作曲されたブランデンブルク協奏曲第5番との関係性も指摘されている。全6曲のうち5曲までが「教会ソナタ形式」(緩・急・緩・急)の4楽章によって構成されており、「バロック音楽の総括者」と称されるバッハらしい多彩な作品集になっている。
第4番
ハ短調。チェンバロが奏でる分散和音にのって、ヴァイオリンがシチリア舞曲風のメロディを歌う第1楽章。その旋律は《マタイ受難曲》のアリア「憐れみたまえ」にも似て、悲壮美が際立つ。バッハの音楽が凝縮されたかのような第2楽章は、全6作品中もっとも規模の大きな半音階的フーガ。第3楽章のアダージョは穏やかな哀愁が魅力的。終楽章は二部構成のフーガ。全曲を通して、ひとつの旋律を変奏曲のように扱っているという指摘もある。
第5番
ヴァイオリン奏者には難曲とされるヘ短調。第4番と同様、全体が深い憂愁に包まれている。その理由に、最初の妻マリア・バルバラの死をあげる見方もある。リトルネッロ形式を用いた第1楽章には、テンポの指定がない。第2楽章は力強い3声のフーガ。アダージョの第3楽章は、ゆったりと繰り広げられるヴァイオリンの重音奏法が苦悩の色を醸し出す。第4楽章は舞曲を想わせる快活な3声のフーガ。シンコペーションのリズムが印象的だ。
第6番
ト長調。本曲のみ5楽章制が採られ、冒頭に急速なアレグロ楽章を置いている。イタリア的な色彩が濃く、ヴァイオリンのソロとチェンバロのトゥッティが協奏曲的で、華やかな音楽を聴かせる。第2楽章以降は、通常の教会ソナタ形式。情感あふれるラルゴの第2楽章。第3楽章はブランデンブルク協奏曲第5番を想起させるチェンバロのみの音楽。シンコペーションが憂愁を増す第4楽章アダージョ。フーガの第5楽章で明るく快活に曲を閉じる。
第1番
ロ短調。ヴァイオリンが荘重なメロディを奏でるこの作品は、幼くして亡くなった息子アウグストとの関連を論ずる向きもある。声楽のアリアのようにヴァイオリンが扱われる第1楽章は、5つの声部から構成されており、すでにトリオ・ソナタの域を脱している。重苦しい熱狂すら感じさせる第2楽章アレグロはソナタ形式を予感させ、伸びやかな第3楽章では幸福感と苦悩の表情が交錯する。第4楽章アレグロも重さと軽さが錯綜する二部構成のフーガ。
第2番
イ長調。第1楽章は穏やかな雰囲気を湛えた典型的なトリオ。対位法の扱いにバッハの技巧の粋がうかがえる。なお、この楽章にもテンポの指定がない。それとは対照的な第2楽章は、華麗なコンチェルト・グロッソを想わせるアレグロ。演奏者のヴィルトゥオージティが発揮される。アンダンテの第3楽章は、たおやかな悲しみを歌い上げるヴァイオリンとチェンバロの二重奏。フーガの味付けがなされた終楽章は、快活なプレスト。
第3番
ホ長調。壮麗な音楽を聴かせる第1楽章アダージョ。伴奏であるにもかかわらず5声部で書かれたチェンバロこそ主役かも知れない。協奏曲的なスケール感は、オーケストラをもイメージさせる。フーガの厳しさよりも、雅やかな遊戯を想わせる第2楽章アレグロ。長大な変奏が行なわれるシャコンヌの第3楽章では、チェンバロが旋律を奏でるとき、ヴァイオリンが重音で伴奏にまわる。そして3つの声部が協奏的に駆けめぐる華麗な終楽章が続く。
主催:東京・春・音楽祭実行委員会 共催:東京国立博物館 協力:日本音響エンジニアリング株式会社
※掲載の曲目は当日の演奏順とは異なる可能性がございます。
※未就学児のご入場はご遠慮いただいております。
※やむを得ぬ事情により内容に変更が生じる可能性がございますが、出演者・曲目変更による払い戻しは致しませんので、あらかじめご了承願います。
※チケット金額はすべて消費税込みの価格を表示しています。
※ネットオークションなどによるチケットの転売はお断りいたします。
(2018/04/03更新)