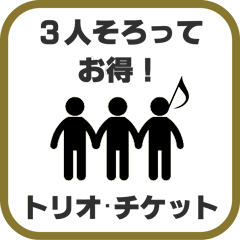東京・春・音楽祭-東京のオペラの森2018-
ミュージアム・コンサートN響メンバーによる室内楽
~ブラームス弦楽四重奏曲 全曲演奏会 III
N響元コンサートマスター山口裕之を中心とした弦楽四重奏。ベートーヴェン全曲演奏を経てブラームスに取り組むシリーズ3回目の公演です。ゲストに川﨑和憲を迎える五重奏では、とりわけ名曲の第2番を。
プログラム詳細
2018:04:10:19:00:00
2018.4.10 [火]19:00開演(18:30開場)
国立科学博物館 日本館講堂
■出演
ヴァイオリン: 山口裕之、 宇根京子
ヴィオラ: 飛澤浩人、 川﨑和憲*
チェロ: 藤村俊介
■曲目
シューマン:弦楽四重奏曲 第3番 イ長調 op.41-3
I. Andante espressivo - Allegro molto moderato
II. Assai agitato - Un poco adagio - Tempo risoluto
III. Adagio molto
IV. Finale. Allegro molto vivace - Quasi Trio
ブラームス:
弦楽四重奏曲 第2番 イ短調 op.51-2
I. Allegro non troppo
II. Andante moderato
III. Quasi menuetto, moderato
IV. Finale. Allegro non assai
弦楽五重奏曲 第2番 ト長調 op.111*
I. Allegro non troppo, ma con brio
II. Adagio
III. Un poco allegretto
IV. Vivace ma non troppo presto
[アンコール]
ブラームス:弦楽五重奏曲 第2番 ト長調 op.111 より 第1楽章 Allegro non troppo, ma con brio
【試聴について】
シューマン:弦楽四重奏曲 第3番
ピアノ五重奏曲など数々の名曲が生み出され、「室内楽の年」と称される1842年の作品。7月22日に完成され、3曲セットの作品41として出版された。公にはメンデルスゾーンに献呈されているが、自筆譜には「愛する我が妻クララの誕生日に」と記されている。初演はクララの誕生日に内輪のパーティーで行なわれ、メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲の初演者としても知られるフェルディナンド・ダヴィッド率いるカルテットが演奏を受け持った。ゆったりとした序奏を持ち、ヴァイオリンの歌にあふれた第1楽章はソナタ形式。冒頭の音名は「ラ・レ」で、これはクララの「C・la・ra」を象徴している。心のざわめきと激しい高揚が感じられる第2楽章は変奏曲。ヴァイオリンとヴィオラで交わされる歌が哀しくなるほど美しい第3楽章は、ソナタ風のアダージョ。そして、ロンド形式の終楽章は、四人が飛び跳ねるような民族舞曲を競演する。ベートーヴェンに範を採ったとされるが、全体を覆う優美な繊細さはシューマンの音楽そのものと言えよう。
ブラームス:弦楽四重奏曲 第2番
作曲期間は1860年代後半から73年にかけてで、熟考を重ねた末に完成された作品。第1番とともに作品51として出版され、アマチュア音楽家であり、友人で外科医のテオドール・ビルロートに献呈された。初演は1873年にウィーンで行なわれた。ソナタ形式の第1楽章はもの憂げな表情で始まるが、第1番のように全体を包むエキセントリックな重苦しさはない。この対照的な作風は、しばしば「悲劇的序曲」と「大学祝典序曲」とも比較される。随所にヴァイオリンによる伸びやかな歌が聴かれるが、冒頭でヴァイオリンが奏でる「F・A・E」の音列は、ヨーゼフ・ヨアヒムがモットーとした「自由・だが・孤独(Frei aber einsam)」に由来している。ブラームスがこの時期、大ヴァイオリニストの親友に、いかに多くを負っていたかを物語るエピソードである。渋い男のロマンを奏でる第2楽章モデラート。生真面目な戯れのなかに優しいメロディが隠された第3楽章クアジ・メヌエット。ロンド形式による終楽章は、第1ヴァイオリンが全体を牽引しながら、シンフォニックな広がりを感じさせてくれる。
ブラームス:弦楽五重奏曲 第2番
作曲は1890年の夏で、同年ウィーンで初演された。編成はヴァイオリン2、ヴィオラ2、チェロ。アレグロ、アダージョ、アレグレット、プレストの四楽章からなり、当初は交響曲第5番として構想されたと伝えられる(交響曲第4番の初演は5年前の1885年)。そのためか、音楽の重心が低く、全体を通してヴィオラが活躍し、ハンガリー・ロマ風の魅力的な主旋律を聴くことができる。さらに、あるときはクラリネットを、またあるときはホルンを思わせる音色とメロディラインは、小さなオーケストラを彷彿とさせ、聴きながら自ずとオーケストレーションが思い浮かぶかもしれない。曲全体が人生の黄昏時を感じさせる哀愁に包まれているが、ところどころに若々しい情熱がふと顔をのぞかせる。なかでも荒々しい終楽章は、ブラームスの代名詞ともなったハンガリー舞曲を想起させ、圧倒的な高揚感を持って曲を締めくくる。
主催:東京・春・音楽祭実行委員会 共催:国立科学博物館
※掲載の曲目は当日の演奏順とは異なる可能性がございます。
※未就学児のご入場はご遠慮いただいております。
※やむを得ぬ事情により内容に変更が生じる可能性がございますが、出演者・曲目変更による払い戻しは致しませんので、あらかじめご了承願います。
※チケット金額はすべて消費税込みの価格を表示しています。
※ネットオークションなどによるチケットの転売はお断りいたします。
(2018/04/11更新)