春祭ジャーナル 2018/01/24
国立西洋美術館の主任研究員に聞く
「プラド美術館展 ベラスケスと絵画の栄光」&記念コンサートの魅力
今年も東京・春・音楽祭では、上野エリアの美術館や博物館とのコラボレーションによるさまざまなコンサートが予定されています。国立西洋美術館では、「プラド美術館展 ベラスケスと絵画の栄光」記念コンサートを開催。スペイン王室コレクションのバロック美術を中心とした展覧会にちなんで、バロック・ハープの魅力を味わう二つの演奏会が行われます。
スペイン美術史を専門とし、コンサート当日お話を聞かせてくれる国立西洋美術館主任研究員の川瀬佑介さんに、展覧会のみどころやスペイン美術の魅力について、お話を伺いました。
文・高坂はる香(音楽ライター)

川瀬佑介さん
©Koichi Doyo
一番の見どころは、スペイン王室と密接にかかわり、スペイン美術の黄金時代と呼ばれる17世紀に活躍した重要な画家、ディエゴ・ベラスケスの7点の作品です。
過去のプラド美術館展でもベラスケスの作品が何点か来たことはありますが、いずれも小品でした。それが今回は、人物の全身が描かれた大型の作品が多く、そのうえ王様や皇太子の肖像といった重要なものばかりです。プラド美術館には、ベラスケスの全作品の三分の一ほどにあたる40点強が所蔵されていますが、国民的画家としての重要性から、これだけまとまった数の作品が貸し出されるのは稀なことです。ベラスケスの画業全体を見渡すことができると思います。
ディエゴ・ベラスケス
《狩猟服姿のフェリペ4世》
1632-34年 マドリード、プラド美術館蔵
© Museo Nacional del Prado
バロック時代の他の国、例えばイタリアやフランスの王たちと比べて、スペイン王室の趣味は質実剛健です。例えば、希代の美術コレクターで、スペイン王室の膨大な絵画コレクションを築く最大の功労者だったフェリペ4世もそんな趣味嗜好を持っていました。ベラスケスが描いた、狩場で休憩するフェリペ4世の姿は、宝石で飾られることも、山盛りの獲物が添えられることもなく、地味な色で描かれ、この人物自身の持つ荘厳さで権力の強さが表されています。見た目の華やかさではなく、余計なものを足さないことで力を示す方法を好んだのです。
フェリペ4世は、芸術家の才能を花開かせる良きパトロンでした。ベラスケスも、彼と出会ったことで才能が正しい方向に導かれたと言えるでしょう。
まずは、イタリア、ルネサンス期の画家、ティツィアーノの《音楽にくつろぐヴィーナス》。彼はダ・ヴィンチやミケランジェロなど、同時代のビッグネームに比べて名前は知られていないかもしれませんが、後世の画家が目標とした存在です。神聖ローマ帝国の皇帝でありスペイン王だった、カール5世という当代最高の権力者に可愛がられ、騎士の称号も受けました。作風においては、雰囲気の魔術というものを開拓した一人といえます。ベラスケスも彼の作品から多くのことを学んだはずです。
それに、ティツィアーノの作品をいくつ持っているかは、コレクターや権力者のコレクションの価値基準のひとつと見られてきたんですよ。例えばダ・ヴィンチの作品では、全体の点数が少なすぎて基準になりえません。ところがティツィアーノは多くの作品を残し、ある時代までは求めれば買えるものでしたから、趣味の良さ、美術知識の高さと財力を示すうえでのバロメーターとなったわけです。
また、バロック期の外交官でもあったフランドルの画家、ルーベンスも、フェリペ4世はじめ当時の王たちに愛されました。彼は外交官としてマドリードにやってきたので、画家として才能を評価されただけでなく、宮廷人としても王や貴族と対等にわたりあうことができたわけです。彼にも後進たちは憧れました。
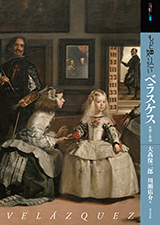
大髙保二郎・川瀬佑介 著
『もっと知りたいベラスケス』
(東京美術)
そうですね。17世紀に、ヨーロッパ各地の重要な流派の絵画が一度に最もたくさん見られる場所といえば、ローマやパリなどではなくマドリードでした。おかげで、ベラスケスはマドリードにいながらにしてティッツィアーノやルーベンスの絵から学ぶことができました。
その意味で今回の展覧会のポイントのひとつは、スペイン宮廷が美術学校のような役割を果たし、その中で生まれた美術を見られる点にもあります。
スペイン美術史を語る上でベラスケスはとても重要な存在ですが、スペイン人芸術家の影響だけを見ていては、彼の実像は見えません。彼は国際的な美術コレクションの影響で生まれた画家なのです。このあたりは、1月30日に発売となる書籍、大髙保二郎・川瀬佑介 著『もっと知りたいベラスケス』(東京美術)で詳しく紹介しています。
ディエゴ・ベラスケス
《王太子バルタサール・カルロス騎馬像》
1635年頃 マドリード、プラド美術館蔵
©Museo Nacional del Prado
バロック美術には、王などの権威を称賛するもの、カトリックと密接に結びついたものがあります。
権威を象徴する作品は、豪華だったり、だまし絵のような手法で立体的に描かれていたりします。例えば、ベラスケスによる皇太子カルロスの騎馬像は、普通に眺めると馬が寸詰まりに見えますが、壁の高い位置にかけると、跳躍し、飛び出してくるように見えます。こうした表現は、バロック絵画の典型的なものです。
カトリックと密接に結びついた作品のほうでは、対抗宗教改革の時代だったことから、カトリックの教えをいかに伝えるかが意識されています。当時のカトリックは、自らの教義や信仰のあり方を見直し、プロテスタントが認めないことを認めていこうとしました。例えば、マリア様の存在を神として再び認めることもその一つで、そのために聖家族の絵が多く描かれたわけです。
スペインでは、この時代にマリアの夫ヨゼフに対する信仰も高まり、そうした風潮を反映した聖家族の絵画も制作されました。フランドルの画家、ルーベンスがマリア様を中心に描いているのに対して、ムリーリョの《小鳥のいる聖家族》では、若返った父親のヨセフが家族の中心に描かれています。カトリック教会は、民衆にとっての模範となる家族の姿を聖家族に求め、より現実的な父親の姿をヨゼフに反映させようとしたのです。こうしたキリスト教図像の刷新は、バロック美術を特徴づける大きな要素のひとつです。
同じ時代の芸術でも、別の分野をからめて話をすることは簡単ではありませんが、記念コンサートでは音楽好きの方にも楽しんでいただけるお話ができたらと思います。
ペーテル・パウル・ルーベンス
《聖アンナのいる聖家族》
1630年頃 マドリード、プラド美術館蔵
© Museo Nacional del Prado
バルトロメ・エステバン・ムリーリョ
《小鳥のいる聖家族》
1650年頃 マドリード、プラド美術館蔵
© Museo Nacional del Prado
谷中の朝倉彫塑館は、当時のアトリエの雰囲気が残された空間で作品を見ることができておすすめです。あと、ランチで気に入っているのは、山家(やまべ)というとんかつ屋さん。リーズナブルな値段なのに、とてもおいしいです。
暗い、ですね(笑)。スペイン人というと、ラテン気質で陽気なイメージがあるかもしれませんが、例えばイタリア人が根っから陽気なのに比べて、スペイン人は根暗なところがあると思います。人も芸術も光と影のコントラストが強く、影の部分がたくさんあるところに魅力を感じます。
~国立西洋美術館で開催する公演~
「プラド美術館展」記念コンサート