東京・春・音楽祭-東京のオペラの森2018-
ミュージアム・コンサート「プラド美術館展」記念コンサート vol.1
西山まりえ (バロック・ハープ) & 阿部早希子 (ソプラノ)
バロック・ファン垂涎のスペインの至宝たちの展覧会を記念して開催する2日間のコンサート。バロック・ハープの魅力を余すところなくお届けします。
プログラム詳細
2018:03:26:14:00:00
2018.3.26 [月]11:00開演(10:30開場)/14:00開演(13:30開場)[各回約60分]
国立西洋美術館 講堂
■出演
バロック・ハープ:西山まりえ
ソプラノ:阿部早希子
お話:川瀬佑介(国立西洋美術館 主任研究員)
■曲目
伝L.R.デ・リバヤス(1626- after 77):エスパニョレタスとタランテラ[ハープ・ソロ]
A.M.イ・コル(c.1680- c.1734):ラス・フォリアス[ハープ・ソロ]
J.マリン(c.1619-99):
瞳よ、私を蔑むのなら
そんな風に思わないで、メンギーリャ
G.フレスコバルディ(1583-1643):第三旋法のトッカータ[ハープ・ソロ]
C.モンテヴェルディ(1567-1643):苦しみはかくも甘く
A.ファルコニエーリ(1585/86-1656):
甘美なる旋律[ハープ・ソロ]
ああ、限りなく美しい髪よ
J.イダルゴ(1614-85):愛が彼女たちをまごつかせる
※ 当初発表の曲目より、一部変更となりました。
[アンコール]
J.イダルゴ:ああそうだ いやちがう
【試聴について】
~春祭ジャーナル~
チケットについて チケットについて
■チケット料金(税込)
| 席種 | 全席自由 |
|---|---|
| 料金 | ¥3,100 |
 コンサート当日、「プラド美術館展」をご覧いただけます。
コンサート当日、「プラド美術館展」をご覧いただけます。■発売日
一般発売:2017年12月7日(木)10:00

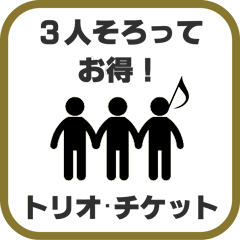
西山まりえ (バロック・ハープ)
本日は画家ディエゴ・ベラスケス(1599-1660)の生涯にちなんだプログラムをお届けする。彼はスペインに生まれ、若くして王室付き宮廷画家となるが、30歳でイタリアへ赴き、ヴェネツィア、フェラーラ、そしてローマに滞在した。なお、17世紀スペインでは黒鍵と白鍵2列が真ん中でクロスするハープが主流だった。しかし当時の文献によると、本日演奏するアルパ・ドッピア(バロック・ハープ)という、弦がクロスしない3列弦のイタリア製ハープがすでにスペインに渡っていたとある。「スペインのハープはよく弦が切れるが、イタリアのハープは切れが少ない」という賛辞も見られた。彼が故郷スペインで触れた音楽、イタリア各地で出会った新しい音楽、帰国後再び耳にした自国のサウンド、というようにベラスケスの人生の流れに沿って、イタリアのバロック・ハープと歌で当時の音楽を再現する。
A.M.イ・コルは、ベラスケスが亡くなったあとに活躍した音楽家。彼が生まれる以前から人気が高かった作品や当時の流行曲を編纂し、「音楽の花(Flores de Música)」を出版した。「ラス・フォリアス」は、スペインはもちろん、ヨーロッパ諸国でもこのスペイン風の代表的な和声進行が大流行し、様々な変奏が施された。
L.R.デ・リバヤスは、ハープ奏者。その著書「音楽の光明と指針(Luz y Norte Musical)」には、ハープやギターの手引き、音楽理論、応用としていくつかの作品が挿入されている。その多くは当時流行していた「エスパニョレタス」や「タランテラ」など舞曲を編纂したものである。
J.マリンは、マドリードで活躍したテノール歌手。殺人や強盗の罪で投獄されたこともあるが、当時彼への評価は大変高いものであった。「瞳よ、私を蔑むのなら」や「そんな風に思わないで、メンギーリャ」など、彼の歌曲はギター伴奏、あるいは通奏低音がついている。
G.フレスコバルディは、フェラーラで生まれ、ローマのヴァチカン大聖堂オルガニストに抜擢されたスター的鍵盤奏者。この「第三旋法のトッカータ」など、トッカータ、リチェルカーレ、カンツォンは、後の時代の音楽家たちにも影響を与えた。
C.モンテヴェルディは、イタリアのクレモナ生まれ、マントヴァ宮廷楽長とヴェネツィアのサン・マルコ寺院の楽長を歴任し、音楽様式に新しい変革をもたらした17世紀イタリアを代表する作曲家。「苦しみはかくも甘く」は、1624年にC.ミラヌッツィが歌曲集「第4巻アリア風の愛らしさ」に収めた、モンテヴェルディの歌曲である。
A.ファルコニエーリは、ナポリに生没したリュート奏者だが、その生涯においてパルマやフェィレンツェで活躍し、フランスとスペインにも旅をした。「甘美なる旋律」や「ああ、限りなく美しい髪よ」などはスペインで演奏され、ベラスケスも耳にすることがあったかもしれない。
J.イダルゴは、宮廷礼拝堂のハープとチェンバロ奏者。彼は宮廷の中で最も気に入られていた音楽家で、彼の名声の高さはスペイン、ポルトガル、ラテンアメリカなど各地にその作品の写譜が残っていることからも証明される。彼は自身の手紙に「世俗歌(tono humano)だけに関心を持っている」と書いているが、「愛が彼女たちをまごつかせる」のように、耳に残る印象的な旋律を創る才能があったこともうかがえる。
主催:東京・春・音楽祭実行委員会 共催:国立西洋美術館 協力:読売新聞社/日本音響エンジニアリング株式会社
※掲載の曲目は当日の演奏順とは異なる可能性がございます。
※未就学児のご入場はご遠慮いただいております。
※やむを得ぬ事情により内容に変更が生じる可能性がございますが、出演者・曲目変更による払い戻しは致しませんので、あらかじめご了承願います。
※チケット金額はすべて消費税込みの価格を表示しています。
※ネットオークションなどによるチケットの転売はお断りいたします。
(2018/03/28更新)