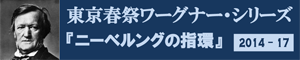春祭ジャーナル 2012/03/03
連載 Wagneriana ワグネリアーナ
~ワーグナーにまつわるあれこれ 3
第3回 ドビュッシーとワーグナー
4月5、8日にワーグナーの歌劇《タンホイザー》を上演する東京・春・音楽祭では、それに先立つ4月1日に、昨年に引き続き「マラソン・コンサート」が開催される。こちらのテーマはドビュッシー。そこで、今回はこの作曲家にスポットを当ててみよう。
クロード・ドビュッシー(1862-1918)は、フランス近代音楽のスターターとも言われる存在。今日の作曲界における世界的ドンのようなピエール・ブーレーズ(1925-)も、ドビュッシーの《牧神の午後への前奏曲》をもって現代音楽が始まったと高く評価している。そんなドビュッシーも、ワーグナーの影響を大きく受けたひとりだった。
ワーグナーへの傾倒
パリと言えばカフェ文化。プセ(chez Pousset)やトメン(chez Thommen)、ヴァシェット(café Vachette)などは、マラルメ邸や"独立芸術書房"と並んで、どれも19世紀末の作家や芸術家たちが寄り集まったミーティング・ポイントとして知られる。ドビュッシーも1887年頃に、プセでヴィリエ・ド・リラダンやカチュール・マンデス、トメンでモーリス・ロリナやガブリエル・ヴィケール、ヴァシェットでジャン・モレアスといった作家と知り合い、親交を深めた。ドビュッシーが、リラダンの戯曲『アクセル』やマンデスの『ロドリーグとシメーヌ』を音楽作品にしようと試みたのは、こういった交友がきっかけである。
さて、前回のコラムでも触れたようにリラダンもマンデスも熱狂的なワグネリアンであるが、彼らがドビュッシーを同じ趣味嗜好に引き込んだわけではない。ドビュッシーがワーグナーを知るようになったのは、はっきりした時期こそ特定できないものの、1885年に留学先のローマのアポロ劇場で《ローエングリン》、さらに87年にはラムルー管の公演で《トリスタンとイゾルデ》第1幕に接した記録が残っているので、それなりに早かったはずだ。そもそも音楽を専門に学んでいたわけだから、学生時代にワーグナーに触れていたと考えるのは至極普通のことだろう。すでに80年代初期にはヴィーンで《トリスタン》を観劇し、かつそのスコアを所有して丸ごと暗記していたという逸話も残っている程だ。
彼が初めてバイロイトを訪れたのは、1888年。当時の彼にとって、この"聖地"を訪問するのは経済的に不可能な状態だったが、音楽好きの銀行家エチエンヌ・デュパンの援助で実現した。この最初の"バイロイト詣で"で《パルジファル》と《ニュルンベルクのマイスタージンガー》を鑑賞。特に《パルジファル》では、作品そのものに魅せられただけでなく、そこで耳にしたこの劇場ならではの音響の妙に相当に衝撃を受けたという。
1889年8月には、デュカスやショーソンらと2度目のバイロイト旅行。《トリスタン》を観劇している。
まさにどっぷりとワーグナーにハマっていたのだろう。この当時書かれた《ボードレールの詩による5つの歌》には、ワーグナー風のテイストが色濃く漂っている。
歌劇《ペレアスとペリザンド》
バイロイトでワーグナー熱を喚起されたドビュッシーは、劇音楽やオペラに再び目を向け、《アクセル》や《ロドリーグとシメーヌ》に着手した。それらはあいにく実を結ぶことはなかったが、1893年にはモーリス・メーテルランク(1862-1949)の戯曲を台本としてチャレンジし、1902年に遂に完成させる。それこそが、ドビュッシー自身が唯一完成させたオペラ、《ペレアスとメリザンド》である。
この作品からは、ワーグナーからの影響と、それからの脱却というアンビヴァレントな姿が色濃く見受けられる(ワーグナーへの畏怖と尊敬、そして反発という心情は、書簡集や著作などにも頻繁に登場する)。
そもそも物語自体、2人の身内男性(ゴローとペレアス)と、他所からやって来たひとりの女性(メリザンド)による三角関係という設定が《トリスタンとイゾルデ》を彷彿させる---というかそっくり(ちなみにドビュッシーは、後の1907年から10年にはベディエの編んだ『トリスタンとイゾルデ』をオペラ化しようとまでしていた)。
また、作曲技法的にも、ライトモティーフを用いている点がまさにワーグナー風だ。ライトモティーフとは、物や人、概念やシチュエイションなどに対応させた特定の旋律や楽節のことで、日本語では「示導動機」などと訳される。それを適宜用いて、音だけで状況や心情をイメージさせたり理解させるというわけだ。ワーグナーは諸作品で"聖杯"や"聖槍"、"ヴァルハラ(=城)"、"ジークフリート"、"ノートゥング(=剣)"、"愛"、"憧憬"、"死"など、数々のライトモティーフを利用しているが、ドビュッシーもこの《ペレアス》で、"ゴロー"や"アルケル"など各登場人物の他に、"森"、"指輪"、"水"、"抵抗"、"不安"、"長い髪"、"疑い"、"涙"、"羊"、"罠"、"目覚め"、"承諾"、"子供"......などなど、実に様々なモティーフをあてがっている。その他にも、《パルジファル》との音楽的な類似が指摘されることも多い。
しかし、天才ドビュッシーのこと。先達の手法を真似るだけでは留まらない。
ドビュッシーは師であるエルネスト・ギロー(1837-92)との対話の中でこう語っている。「従来のオペラは歌い過ぎる。音楽的な衣装が重過ぎる。自分の理想はカマイユ(単色画法)やグリザイユ(モノクローム)のようなタイプなのです」。つまり、ワーグナーのように強くストレートに主張するのではなく、それとなくわからせるような淡い表現を好んだ。そのため、ワーグナーとドビュッシーのライトモティーフの用法の違いは---きわめて大雑把に言ってしまうのならば---ドビュッシーの方は、和声付けや変形によってぼかすことで、より暗示的に用いられることにある。
かくしてドビュッシーはオリジナリティを獲得する。「名声を博した音楽家、もしくは現代の芸術家は、ただひとつのことにしか心を砕きはしません。それは個人的な作品、可能な限り目新しい作品を作るということです」(ドビュッシー)。
とはいえ、ゴローの動機などいくつかのモティーフはやはり全編でかなり耳につくし、完全に脱却したと言い切れるわけでもない。この呪縛と脱却の抗いが、この作品の興味深いところのひとつなのだ。いずれにしても、ワーグナーの強烈な世界に一度どっぷりと浸かったからこそ、後のドビュッシーらしさがより一層研ぎ澄まされたのは間違いない。
その他
ドビュッシー作品に見出せるワーグナー的な音楽的要素は、他にもある。先に挙げた《ボードレールの詩による5つの歌》もそのひとつで《トリスタン》的だし、たとえば、自作のテクストを用いた《抒情的散文》の第1曲「夢に」には、「グラール(聖杯)を求める騎士」といった歌詞まで出てくる。
《子供の領分》も有名だ。最後に置かれた第6曲「ゴリウォーグのケイクウォーク」の中間部には、《トリスタン》前奏曲冒頭のチェロの一節---憧憬のモティーフ---が現れる。おまけにそこには、ご丁寧に「avec une grande émotion(感情たっぷりに)」と指示まで付けられてい程だ。
これら、「夢に」も「ゴリウォーグのケイクウォーク」も、(かつ《牧神の午後への前奏曲》も)東京・春・音楽祭のマラソン・コンサートで演奏されるので、是非ナマの演奏でお聴きいただきたい(演奏者陣も選り抜きのメンバー!)。ついでに書き添えておくと、ドビュッシーの命日は3月25日。この作曲家を聴き、思いを馳せるのにこれまたちょうどよい時期、とも言えるのではないだろうか。
【参考文献】
『ドビュッシー音楽評論集~反好事家八分音符氏(ムッシュー・クロッシュ・アンティディレッタント)』(平島正郎 訳)岩波文庫
『ドビュッシー書簡集1884-1918』ルシュール編(笠羽映子 訳)音楽之友社
『音楽のために~ドビュッシー評論集』(杉本秀太郎 訳)白水社
『ペレアスとメリザンド』メーテルランク(杉本秀太郎 訳)岩波文庫
第1回 ワーグナーへのオマージュ(1) |
第2回 フランス文学界のワグネリアンたち |
第3回 ドビュッシーとワーグナー |
第4回 《マイスタージンガー》と映画
~関連公演~
【2014】
【2013】
【2012】
東京春祭マラソン・コンサートvol.2 ドビュッシーとその時代~生誕150年に寄せてー芸術都市・パリに生きたアーティストたち