お知らせ 2016/04/12
充実の「公式プログラム」を手に音楽祭を堪能しよう!
東京・春・音楽祭では、今年も豪華&多分野の執筆陣による書き下ろしエッセイ/公演解説が詰まった充実の公式プログラムを会場でご用意しております(1冊500円)。
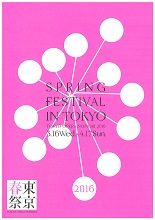 以下、ラインナップをご紹介いたします(掲載順/カッコ内は執筆者です)。
以下、ラインナップをご紹介いたします(掲載順/カッコ内は執筆者です)。
■私の夢舞台・上野(松平定知 京都造形芸術大学教授(元NHKアナウンサー))
■ボイトとヴェルディ(吉田光司 音楽評論家)
■大人になるということ─教養小説としての《ジークフリート》(山崎太郎 東京工業大学教授 ドイツ文学)
■作曲家兼オルガニスト、モーリス・デュリュフレ(井上さつき 愛知県立芸術大学教授)
■「万人のため」を貫いた、超売れっ子作曲家(寺西 肇 音楽ジャーナリスト)
■タンゴの真髄(高場将美 音楽評論家)
■訳詞家、近藤朔風(山東 功 大阪府立大学教授)
■《月に憑かれたピエロ》とバッハの影(樋口隆一 音楽学者・指揮者)
■アイルランドと音楽(喜多尾道冬 ドイツ文学者)
■シェイクスピア劇と歌(松岡和子 翻訳家・演劇評論家)
■レーラ・アウエルバッハは菩薩である(宮山幸久 キングインターナショナル・プロデューサー)
■シェイクスピアの女性、道化、歌曲(前島秀国 サウンド&ヴィジュアル・ライター)
■ストラヴィンスキーとドゥシュキン─活路を支えた同郷人コミュニティ(中田朱美 音楽学)
■より不思議な《冬の旅》(梅津時比古 桐朋学園大学学長)
■オリジナル~編曲~変奏(オットー・ビーバ ウィーン楽友協会資料館館長)
■ベートーヴェンとロマン派の室内楽の系譜(西原 稔 桐朋学園大学教授、音楽学)
■モーツァルトに「初期」なんてあるのか─「初期弦楽四重奏曲」雑感(森 泰彦 くらしき作陽大学准教授・音楽学)
■ヴァイオリンの魅力が詰まった小品(前橋汀子・談)
■ベルリン・フィル奏者の室内楽活動(山崎浩太郎 演奏史譚)
■運命的な作品と出会った留学時代(前橋汀子・談)
■ポーランド音楽?(関口時正 ポーランド文学翻訳家)
■新しい音楽を目指して─ポリーニ・プロジェクトに寄せて(笠羽映子 早稲田大学教授)
■歌う楽器・オーボエ(飯尾洋一 音楽ジャーナリスト)
■70年代~90年代の洋楽ロック史(和田博巳 音楽評論家、オーディオ評論家)
■レスピーギ、夢想の設計(原口昇平 音楽文芸、翻訳家)
■ベートーヴェンとチェロ(前編)(中村孝義 大阪音楽大学教授、音楽学)
■イギリスで花開いた英語オペラとイタリア語オペラ(佐々木勉 音楽学)
■畏敬と憧憬の狭間で(浅岡弘和 音楽評論家)
■ベートーヴェンとチェロ(後編)(中村孝義 大阪音楽大学教授、音楽学)
■歴史ある世界的コンクールで実力を認められた荒木奏美(片桐卓也 音楽ライター)
■サクソフォンの歴史(余田安広 ミュージックライター)
■40億年、そして400年(折原 守 神奈川県民ホール館長、国立科学博物館名誉館員)
■ブラームスの弦楽四重奏曲(佐藤康則 音楽評論家)
■未来を担う逸材(木幡一誠 音楽評論家)
■アルベルト・ツァーベルとハープ(高田明洋 高田ハープサロン)
■ホルンとリヒャルト・シュトラウス(広瀬大介 音楽学、音楽評論)
■ハルヴォルセンの「パッサカリア」(寺西基之 音楽評論家)
■和声の旅(オデュッセイ)─コルトベルク変奏曲(堀 朋平 音楽学)
■安定と夢幻のあわいに─無伴奏チェロ組曲の奥行き(堀 朋平 音楽学)
■宇宙につながるヴァイオリン─バッハの無伴奏作品(堀 朋平 音楽学)
■既知のものと戯れる─バッハと編曲の美学(堀 朋平 音楽学)
■ルネサンスの春を生きた画家ボッティチェリ(松本典昭 ヨーロッパ文化史研究家、阪南大学教授)
■メディチ家と音楽家たち(米田潔弘 桐朋学園大学教授 西洋史)
■生誕300年 伊藤若冲─枯れることのなかった創作力(平方正昭 東京都美術館 学芸員)
■カラヴァッジョとその時代(川瀬佑介 国立西洋美術館 研究員)
■バウハウスと前衛音楽(眞壁宏幹 慶應義塾大学教授)
■「小さな象さん」の物語(永井玉藻 音楽学)
■ムーティと友情の道─日伊国交樹立150周年記念オーケストラ(田口道子 日伊文化交流コーディネイター)
■シリーズ◎上野ものがたり 第2回 夏目漱石と上野(瀧井敬子 音楽学・音楽プロデューサー)
公式プログラムにはこのほか、本公演・桜の街の音楽会・東京春祭 for Kids のスケジュールや出演アーティストのプロフィールを収録しております。