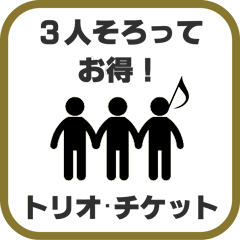東京・春・音楽祭-東京のオペラの森2018-
ミュージアム・コンサート北川 翔 (バラライカ) & 大田智美 (アコーディオン)
ロシアはもとより国内のメディアでも活躍する新進気鋭のバラライカ奏者と、国内外でクラシック、現代音楽等様々なジャンルで新しい可能性を追求し続けるアコーディオン奏者。新しくて楽しめるデュオが、多岐にわたるプログラムをお届けします。
プログラム詳細
2018:04:13:19:00:00
2018.4.13 [金]19:00開演(18:30開場)
国立科学博物館 日本館講堂
■出演
バラライカ:北川 翔
アコーディオン:大田智美
■曲目
ロシア民謡:月は輝く
A.アリャビエフ:うぐいす
A.シャーロフ:ジプシーファンタジー
ロシア民謡:ともしび
L.クニッペル:ポーリュシカ・ポーレ
A.シャーロフ:ぶどう色のショール
V.ゴロドフスカヤ:カリンカ
ピアソラ:
天使の死
忘却
チャイコフスキー:トレパーク(ロシアの踊り)(組曲 《くるみ割り人形》 op.71a より)
M.ジャール:ララのテーマ(映画 『ドクトル・ジバゴ』 より)
G.カッチーニ:アヴェ・マリア
ハチャトゥリアン:剣の舞
[アンコール]
ロシア民謡:黒い瞳
【試聴について】
ロシア民謡:月は輝く
ロシア民謡の王道を行く曲。明るく照り映える月のもと、恋人の家に向かう若者の溢れんばかりの喜びを歌っている。
A.アリャビエフ:うぐいす
19世紀前半のロシア国民楽派の先駆者アリャビエフが1826年に書いた曲。うぐいす(ナイチンゲール)の鳴き声を模したコロラトゥーラの華麗な技巧が聴き所だが、シベリア流刑の憂き目を見たアリャビエフが、追放者の苦渋の思いを恋の歌に託したとも言われている。
A.シャーロフ:ジプシー・ファンタジー
サンクトペテルブルク音楽院の教授で、バラライカ奏者でもあり、指揮や作曲も行なったアレクサンドル・シャーロフは、ロシア各地に眠っていた古い民謡を収集し、バラライカのための作品を数多く残した。本曲は、有名な「二つのギター」のテーマをもとに作られた幻想曲である。
ロシア民謡:ともしび、ヴォルガの舟歌
「ともしび」は、ソ連時代に流行したロシア民謡で、戦場と故郷とに離ればなれになった若い恋人を描いたもの。作曲者は不詳だが、日本ではロシア民謡として愛好され、新宿には本曲名を冠した歌声喫茶がある。「ヴォルガの舟歌」も、ロシア民謡を代表する曲。ヴォルガ河の舟曳きの歌であり、ロシアの名バス歌手シャリアピンの歌唱により世界的に知られるようになった。
L.クニッペル:ポーリュシカ・ポーレ
1934年に書かれたクニッペルの交響曲第4番《コムソモール戦士の詩》の第1楽章・第2主題が独立して、軍歌として歌われるようになったもの。タイトルは「小さな草原、草原よ」といった意味。
A.シャーロフ:ぶどう色のショール
ロシアの古いロマンスをもとに作られた変奏曲。「ロシア・ロマンス」は、ロシア民謡同様に作曲者不詳のものが多いが、民謡と区別して男女の恋愛を歌ったものを特にそう呼んでいる。
V.ゴロドフスカヤ:カリンカ
花嫁を祝う明るい婚礼歌である。「カリンカ」とは、赤い実のなる低木果樹「カリーナ」の愛称で、花嫁の象徴でもある。古いロシアの婚礼では、その枝が用いられたという。
ピアソラ:天使の死、忘却
ピアソラは、クラシックやジャズの要素を従来のタンゴと融合させて、独自の音楽を創出した。「天使の死」は、劇作家ロドリゲス・ムニョスの舞台作品『天使のタンゴ』のために作曲された、速いテンポのフーガで始まるタンゴ。「忘却」は、マルチェロ・マストロヤンニ主演の映画『エンリコ4世』(1984年)の挿入曲として作曲された。
チャイコフスキー:トレパーク
バレエ音楽《くるみ割り人形》といえば、1892年の初演から100年以上経った今日でも、親しみやすいメロディの数々が高い人気を誇っている。その第2幕で披露される様々なディヴェルティスマンの一つが「トレパーク」。躍動感たっぷりにロシアの踊りを表現している。
M.ジャール:ララのテーマ
1965年の米伊合作映画『ドクトル・ジバゴ』は、ロシアの作家ボリス・パステルナークの原作を壮大なスケールで映画化したもの。そのヒロイン・ララのテーマとして本曲を書いたモーリス・ジャールは、同年のアカデミー作曲賞を受賞した。
カッチーニ:アヴェ・マリア
突如として20世紀末の音楽シーンに現れて有名になった本曲は、当初はイタリア・ルネサンス末期の作曲家ジュリオ・カッチーニの作とされていたが、現代作曲家による模作という説もあり、出自は定かでない。ベラルーシ出身のカウンターテナー、スラヴァの歌唱などを通して世界的に広まった。
ハチャトゥリアン:剣の舞
アラム・ハチャトゥリアンは、グルジア(現・ジョージア)のトビリシ生まれ。彼の名を一躍世界に知らしめたのが、この「剣の舞」である。1942年初演のバレエ作品《ガイーヌ》の最終幕で用いられる曲で、剣を手にしたクルド人の戦いの踊りを描いている。
主催:東京・春・音楽祭実行委員会 共催:国立科学博物館
※掲載の曲目は当日の演奏順とは異なる可能性がございます。
※未就学児のご入場はご遠慮いただいております。
※やむを得ぬ事情により内容に変更が生じる可能性がございますが、出演者・曲目変更による払い戻しは致しませんので、あらかじめご了承願います。
※チケット金額はすべて消費税込みの価格を表示しています。
※ネットオークションなどによるチケットの転売はお断りいたします。
(2018/04/12更新)